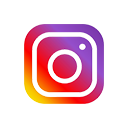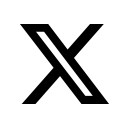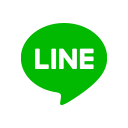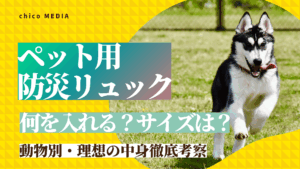「災害が起きたとき、どうやって愛犬を守れば良いの?」と不安を感じていませんか?大きな地震や台風などの自然災害は予測が難しく、いざという時に慌ててしまうことも多いものです。
東日本大震災や熊本地震では、悲しいことにペットと離れ離れになってしまった飼い主さんも多く見られました。いざという時に落ち着いて行動できるよう、被災地でのペットとの過ごし方を事前に知っておくことが大切です。
この記事では、災害時のペット避難の基本的な考え方から、避難所での生活の注意点まで、被災地で愛犬と過ごす際に役立つ情報を総まとめしています。愛犬の命と安全を守るために、飼い主さんが今から備えておきたいことを一緒に確認していきましょう。
災害時のペット避難の基本的な考え方

災害が発生した時には、私たちも動揺しますが、愛犬たちはより不安を感じています。そんな時こそ、飼い主さんがしっかりとした知識を持って、冷静に対応することが大切です。
まずは災害時のペット避難における基本的な考え方から理解していきましょう。
「同行避難」が原則
環境省が2018年に策定した「人とペットの災害対策ガイドライン」では、ペットとの「同行避難」が明確に推奨されています。
同行避難とは、まず飼い主さん自身の安全を確保したうえで、愛犬も一緒に避難所や安全な場所へ連れていくことです。
災害時に「ペットは連れていけない」と思い込んで、自宅に置いていったり放してしまったりすることは絶対にしないでください。
一度離れ離れになってしまうと、再会は非常に難しくなってしまいます。「ペットと避難できない」と簡単に諦めず、愛犬との同行避難を基本に準備をしておきましょう。
「同行避難」と「同伴避難」の違い
「同行避難」とは、ペットを連れて安全な場所へ避難することを意味しますが、必ずしも避難所内で一緒の空間で過ごすことを保証するものではありません。一方、「同伴避難」は人間とペットが同じ空間で避難生活を送ることを指します。
多くの避難所では、アレルギーを持つ方への配慮や衛生管理の観点から、人とペットが別々のスペースで過ごすことになっています。通常は建物内の別室や屋外にペット専用スペースが設けられることが多いようです。
愛犬のストレスを考えると一緒に過ごしたいという気持ちはよくわかりますが、こうした避難所のルールを事前に理解しておくことが大切です。
避難所でのペット受け入れ状況を確認する
避難所のペット受け入れ態勢は自治体や避難所によって大きく異なります。ペットの受け入れが可能な避難所であっても、アレルギーを持つ方や衛生面への配慮から、人間とペットの生活スペースが分けられていることがほとんどです。
ただし、盲導犬や介助犬、聴導犬などの補助犬については、同伴避難が義務づけられています。
地域の防災マップや自治体のホームページでペット受け入れ情報を確認したり、地域の防災訓練に参加して実際の状況を把握したりすることをおすすめします。今のうちから、ペット可の避難所が近くにない場合の代替案も考えておくと安心です。車中避難や信頼できる親戚・友人宅への一時避難も選択肢です。動物病院やペットホテルで一時的に預かってくれる場合もあるので、受け入れの可否を事前に確認しておくと安心です。
災害に備えたペットとの避難準備

災害はいつ起こるかわかりません。そんな時、愛犬を守るためにも日頃からの準備が欠かせません。
ここでは、いざという時に慌てないための具体的な準備について解説します。
ペット用防災リュックの準備
ペット用の防災リュックは事前に準備しておくことが大切です。災害発生後は物資が不足するため、愛犬のために十分な備えをしておきましょう。
最も重要なのはペットフードです。少なくとも5日分、できれば7日分以上を用意しておくと安心です。普段食べ慣れているフードがベストですが、缶詰やドライフードなど日持ちするものを選びましょう。持病がある愛犬の場合は常備薬も忘れずに。ケージやキャリーバッグも避難時に必須となります。
その他にも、次のようなものを用意しておくと安心です。
- 予備の首輪とリード(伸びないタイプ)
- トイレシートなどの排泄用品
- 食器
- 飲料水
- 飼い主さんの連絡先や愛犬の健康情報(ワクチン接種状況、既往症など)をメモしたカード
防災グッズをコンパクトにまとめ、すぐに持ち出せる場所に保管しておきましょう。
ペットの迷子防止対策
災害時、パニック状態になった愛犬が脱走してしまうリスクは想像以上に高いものです。平常時から迷子防止対策を徹底することが必要です。
基本となるのは、首輪の状態をこまめにチェックすること。ゆるみがないか、素材が劣化していないかを定期的に確認してください。
鑑札や予防注射済み票、そして飼い主さんの連絡先を記載した迷子札をしっかり付けておくことも重要です。
首輪は災害時に外れてしまう可能性も。より確実な身元証明として、環境省ではマイクロチップの装着を推奨しています。皮下に埋め込むため紛失の心配がなく、飼い主さんの情報が登録されているので確実な身元確認手段となります。
普段からのしつけと訓練のポイント
災害時、周囲に配慮した行動ができる愛犬であれば、避難生活もスムーズです。そのためには日頃からのしつけが何より大切です。
避難先で落ち着いて行動できるよう、次のようなしつけを日頃から行うと良いでしょう。
- 無駄吠えをさせない
- ケージに入る
- 人や他の動物に対して攻撃的にならない
基本的なしつけが、いざという時に大きな差となります。
また、何かあった時に頼れる人を見つけておくなど、緊急時の支援体制を構築しておくと安心です。愛犬のためにも、飼い主さんが冷静に対応できるよう準備しておきましょう。
被災地でのペットとの生活の注意点

被災してしまった場合、愛犬との避難生活には様々な課題が生じます。ここでは、避難所や車中泊など、被災地での愛犬との生活における具体的な注意点をご紹介します。
愛犬と飼い主さん、そして周囲の人々が少しでも穏やかに過ごせるように行動しましょう。
避難所でのペットの飼育ルールとマナー
避難所は様々な状況の方々が共同生活を送る特殊な環境です。ペットを連れている方もそうでない方も、お互いが安心して過ごせるよう、飼い主さんはより一層の配慮と責任ある行動を心がける必要があります。
ペットの世話は全て飼い主さんの責任となりますので、食事や水の補給、排泄物の処理など、全て自分で行う必要があります。トイレシーツや消臭袋、スコップなどを必ず持参し、排泄物は速やかに処理し、指定された場所に捨てるか、持ち帰るようにしましょう。
ペットを連れて共有スペース(トイレ、炊き出し場所など)に立ち入ることは原則として避けてください。やむを得ず通行する場合は、必ずケージに入れるか、しっかりとリードを短く持ち、他の避難者の迷惑にならないよう細心の注意を払いましょう。
ペットのストレスケアと体調管理
災害発生時、私たち人間と同様に、あるいはそれ以上に、ワンちゃんたちは大きなストレスを感じています。慣れない場所、騒音、見慣れない人たち、そして何よりも飼い主さんの不安な様子は、敏感なワンちゃんの負担になります。
避難所では、できるだけ愛犬のそばに寄り添い、優しい声かけ、なでるなどのスキンシップを通して安心感を与えることが大切です。
普段から使っているタオルやおもちゃなど、愛犬の匂いがついた馴染みのあるものを持参すると、ストレス軽減に効果的です。ケージ内には愛犬が落ち着ける空間を作ってあげましょう。
日々の体調変化にも注意が必要です。食欲低下や活動量の減少、異常な鳴き声など、普段と違う様子が見られたら早めにケアしましょう。夏場は熱中症のリスクが高まるため、こまめな水分補給と涼しい場所の確保を心がけてください。
車中避難する場合の注意点
災害時、避難所の状況やペットの特性によっては、やむを得ず車中泊を選択する飼い主さんもいらっしゃるでしょう。車内はプライバシーを確保しやすく、ペットと一緒にいられる安心感がありますが、一方で注意すべき点も存在します。
車内は密閉された空間のため、外気温の影響を非常に受けやすく、急激な温度変化が起こりやすい環境です。ペットは体温調節が苦手なため、細心の注意が必要です。夏場は短時間でも熱中症の危険があります。定期的なエアコンの使用や窓を少し開けての通気確保が必須です。冬場も同様に、寒さ対策としてブランケットなどの保温グッズを用意しておきましょう。
愛犬が運転席周辺に入り込まないよう、ケージやバリアを設置することも大切です。車の乗り降りの際には必ずリードを装着し、ドアの開閉時に脱走しないよう細心の注意を払ってください。窓を開ける際も、ペットが顔や体を出して落下したり、外のものに気を取られて飛び出したりしないよう、開ける幅に注意が必要です。
まとめ

災害時に愛犬と安全に過ごすためには、事前の準備と正しい知識が欠かせません。「同行避難」と「同伴避難」の違いを理解し、お住まいの地域の避難所のペット受け入れ状況を確認しておくことが第一歩です。災害はいつ起こるかわかりません。平常時からの備えが、いざという時の愛犬との安全を左右します。
被災地でペットと過ごす場合の注意点に関してお悩みの飼い主さんは、当サイトで紹介しているペットの防災や緊急時対応に関する他の記事も読んでみてください。
また『chico』雑誌版もオススメなので、まずは内容だけでも見てみてください。大切な家族である愛犬との絆を災害時も守れるよう、今日から準備を始めましょう。